

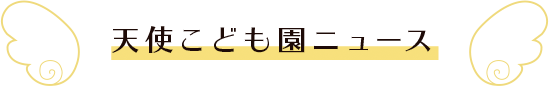
こどもの眼 5月号 園長 早川 成
~ あの手 この手 ~
園長 早川 成
GWが始まる少し前、地区の園長の集まりがありました。
「新年度を迎えて早1か月が経とうとしています…」と、お決まりの挨拶で始まったのですが、問題はそのあとです。「子ども達もそろそろ慣れ、落ち着いてきていることかと思います。」と言葉が続くので、私は心の中で「うそ?マジで?」となりました。
というのも、うちの園ではまだまだ毎朝泣き声が響き渡っていましたし、おんぶに抱っこの光景もあちこちに見られます。また、慣れたら慣れたでやりたいことが増え、行動範囲が広がります。
…と言うわけで、うちの園では泣き声はより強く、動きはより早くなり、落ち着くどころか、日増しにパワーアップしてくるのです。
この違いはいったい何?そもそも、子どもが〝落ち着く〟とは、どんな状態のこと?
そんなことを考えていると、ある小学校から、「今年の子は泣かないと思っていたら、入学して少し経ってから泣いたり渋ったりする子が増えてきました。」と、新一年生の様子が伝わってきました。
私はこの話を聞いて「やっぱりね」と、少し安心しました。そして、当園の子ども達の姿にも「これでいい!」と思いました。
落ち着く時期に違いがあるとしても、大切なのは「どうやって落ち着くか」や「どのようにして落ち着いてくるか」です。
入園式のご挨拶で、毎朝石ころを握りしめてやってきて、門で園長に渡すのが挨拶代わりだった男の子の話をしました。小石を数えてみたら120個ほどありましたので、単純計算だと朝の門のやりとりは半年近く続いたことになります。
思い起こすと、門の手前10mほどの距離に葉っぱを落としておき、拾いながら来ると私にたどり着くという作戦や、機関車トーマスが好きな子と仲良くなるためにトーマスのTシャツを手に入れたこともありました。
新しい靴を履いて来たり髪型が変わっていたりしたときはそれを話題にしてみたり、手品をしたり、踊ってみたり、少しでも園に来るのが楽しみになるように、〝あの手この手〟を工夫して待つのです。
「そのとき」は、突然にはやってきませんが、ふとした時に手応えが感じられることがあります。
もう20年近く前ですが、離れ際に激しく泣く筋金入りの女の子がいました。
なだめてもすかしてもダメなので、お母さんと相談して門で私が預かってバイバイすることにしました。
両腕両足をバタつかせて大暴れする子を肩に抱えて連れて行く姿はまるで人さらいですが、ある日、泣きじゃくるその子に保育室の前で「あれっ何組さんだっけ?」とわざと尋ねてみると、「れもん組」と応えたのです。
一瞬泣き止んで冷静に応える姿に、私はもうすぐその時が来ると予感しました。
〝落ち着く〟とは、聞き分けがよくなったり、我々大人の心配がなくなったりすることではなく、子ども自身が「場所や人に慣れる」「好きな遊びが見つかる」等、安心感を手に入れた結果です。
「仕方なく」や「我慢する」ということではなく、自分で感情や行動をコントロールできるようになり、自分の力で葛藤を乗り越えることが大事だと思います。
ですから、〝あの手この手〟にも「禁じ手」があります。
それは、解決のために「〇〇してあげるから」とニンジンをぶら下げたり、「〇〇買ってあげる」とアメを与えたりすること。
今どきで言えば、「YouTube見ていいから」とスマホを与えることでしょうか。
つまり、ご褒美で釣ると、子ども自身の力にならないと思うのです。
小さい頃はそれでやり過ごすことができても、大きくなってから、「どうしてこんなことに…」「こんなはずじゃなかった!」と自分を見失ったり自暴自棄になったりすると、周囲の力ではどうしてあげることもできません。
それよりも、今のうちから「いろんなことがあるよね」「こんなときもあるさ」と、目の前の出来事を受け入れ、気持ちの落としどころを自分で見つけることができるように、〝あの手この手〟を試しておくことを強くお勧めします。
皆で一緒に、「すったもんだ」を大切にしていきましょう。
©2025 KURUME TENSHI KINDERGARDEN All Rights Reserved.